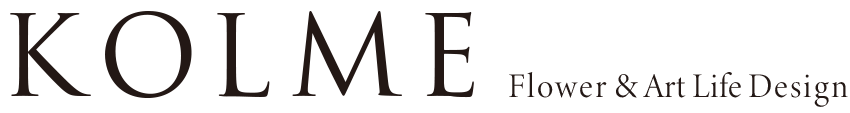銀座の能楽堂で長唄を聴く。 それだけで、日常とは異なる特別な時間が流れ、心が研ぎ澄まされる感覚を覚えました。
先日、大学の先輩方が主宰する「かぎろひの会」第三回演奏会に足を運びました。 会場は、Ginza Sixの観世能楽堂。伝統とモダンが交差するこの場所で、笛・囃子・唄・三味線の四人による演奏が繰り広げられました。
演奏されたのは、創作曲 大地、秋の色種、鷺娘、船弁慶の四曲。
長唄の演奏会というと単調になりがちですが、この日の構成はまさに「魅せる」工夫が凝らされていました。 特に「鷺娘」の四人だけでの演奏は、まるでカルテットのような絶妙なバランス!伝統に新たな風を吹き込む、新鮮なスタイルがとても印象的でした。

長唄の魅力「間(ま)」と、花の「余白の美しさ」
長唄の音楽は、音と音の「間(ま)」を大切にする芸術。 旋律の流れの中に、計算された沈黙があり、そこにこそ深い情緒が宿ります。
この「間(ま)」の美しさは、花の世界にも通じるものがあります。
ブーケを束ねるとき、ただ花を詰め込むのではなく、空間を意識しながら束ねることで、花一輪一輪の美しさが際立つ。 たとえば、パリスタイルのブーケでは、適度な余白を作ることで、花が自然に呼吸し、軽やかな動きを生む。
長唄の間(ま)が音を引き立てるように、花の世界でも「余白」が美しさを引き立てる要素になるのです。
音楽も花も、ストーリーを表現する芸術
長唄の演奏では、同じ曲でも奏者の個性によって違う表現が生まれます。 旋律の間の取り方、三味線の響かせ方、囃子の入り方など—すべてが、演奏者の解釈によって変化します。
これは、花の世界も同じ。
同じ花材を使っても、束ねる人の感性やイメージによって異なるブーケになります。
音楽も花も、「その人だからこそ生まれる表現」がある芸術。 だからこそ、コルメでは、ブーケ作りの技術だけでなく「自分らしい美意識」を育てることを大切にしています。
生の体験が感性を磨く|長唄と花のレッスンの共通点
久しぶりに長唄の演奏会を聴いて、生の舞台の力に心を揺さぶられました。
若い頃は「どう弾くか」に意識が向いていたけれど、今は音そのものを体で受け止める感覚がありました。 音と自分が一体化するような不思議な感覚を覚え、三味線の響きに包まれながら、記憶の中の風景と今の空間が交差する瞬間を味わいました。
これは、花のレッスンでも同じです。
本や写真だけでは伝わらない、実際に花を触り、感じることで気づきを得ることができます。そして、それを繰り返すことで自分の中の美意識が磨かれていきます。
長唄の生演奏が、音楽の持つ本質を改めて教えてくれたように、 ブーケ作りもまた、花に触れることでしか得られない感覚があります。
まとめ 音楽も花も「美意識」を育てるもの
長唄の「間(ま)」と、花の「余白の美しさ」は共通している。
音楽も花も、「その人だからこそ生まれる表現」がある。
生の体験が感性を磨く。音楽も花も、実際に触れ、体感することで理解が深まる。
日本の伝統音楽とフラワーデザイン。 全く異なるように思えるこの二つの世界には、「美を感じる感覚」 という共通点があります。
だからこそ、長唄だけでなく、ジャンルに関わらずに気になった演奏会に足を運び、花に触れる時間を持つことが、 美意識を磨くための大切な時間になるのかもしれません。
また、この感覚を味わうために生の舞台に出かけ、花を束ねる時間を大切にしていきたいです。

フラワーレッスンを初めてみたい方はトライアルレッスンをどうぞ

パリスタイルフラワーで私らしい仕事づくりを叶えたい!作品づくりとビジネスの基礎知識が学べるコースです。