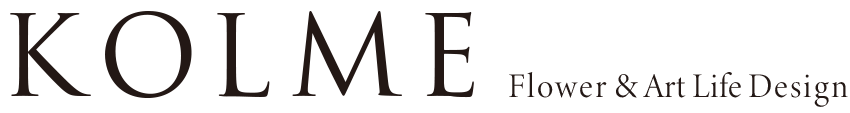初夏のパリ、曇り空からほんの少し光がきらめく午後。
この日は、パリ国立高等音楽院(コンセルバトワール)の卒業演奏会へ向かいました。
ロビーに足を踏み入れる前から、胸の奥で小さなワクワクがはじけていたのを覚えています。

会場へはメインの正面口ではなく、休日用の少しわかりにくい扉から。
工事用の足場が組まれた先で、セキュリティの男性が荷物チェックをしていました。
ホールへ続く、赤い絨毯が敷かれたロビーは、大学というより劇場のようで、自然と背筋が伸びます。
この日の演奏は打楽器。
途中、一曲だけサクソフォーンとの合奏もありました。
打楽器だけの世界は、私には未知すぎて最初は正直とまどいも。
でも音の響きや振動、共鳴、そして“間”を味わうように耳を澄ませるうちに、奏者の頭の中や、どんな楽譜なのか…想像がふくらんでいきます。
サクソフォーンが加わるとメロディーが生まれ、ほっとするような感覚とともに、「どうやって合わせているのだろう?」という新たな疑問も湧きました。

舞台に立っていたのは、華奢な体で全身を使い、四方に置かれた打楽器を力強く叩く若い奏者。
サクソフォーンと向き合う姿からは、これから世界に羽ばたいていく予感が漂っていました。
今回は、この学校に留学している知人のご縁で訪問が実現。
校内を案内してもらい、映画の舞台にもなったという場所も歩きましたが、「どのシーンだったかな?」と誰もはっきり覚えておらず、聖地巡礼にはならなかったのもご愛嬌です。

打楽器の演奏を聴きながら、花の感覚に重ねてみました。
そこにあるのは「流れと切れ味」。
迷いなく手や体が動く瞬間の裏には、入念な譜読みや練習がある。
それは花でいえば、仕上がりをイメージして下準備〜組み立てていく。
表現の世界は、ジャンルが違っても同じプロセスを踏んでいるのだと、改めて感じました。

音楽学校は、建物やそこに存在するものすべてが音楽そのもの。
廊下には無造作にピアノが置かれ、どこからともなく楽器の音が流れてきます。
懐かしさを覚えつつ、国境を越えても同じ空気が漂っていることが心地よく感じられました。