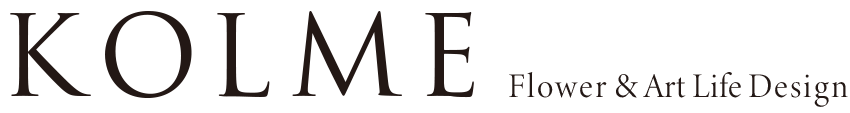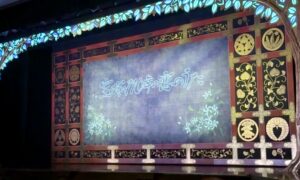「彼の演奏は、一度聴いておいた方がいいよ。」
そんなふうに、数人の友人たちから勧められた永野英樹さんのピアノリサイタル。
とにかく、すごいらしい。
彼が所属している”アンサンブル・アンテルコンタンポラン”というパリのグループは、世界的にも名だたる現代音楽の集団で、日本人がそこに名を連ねているだけでも、本当にすごいことなんだと。
演奏を聴く前から「すごい人なのだ」という期待が高まるばかり。
でも実際に音を浴びた瞬間、
「すごい」なんて言葉じゃ到底足りないと気づきました。
音に包まれる感覚
最初の曲・スカルラッティ「5つのソナタ」が始まった瞬間に浮かんだ感想は、
すごい!
本当に、それしか出てこなかった。
でも、ただの“すごい”では片づけられないから、なんとか言葉にしてみようとするのだけど、もう語彙が足りなくなるくらいの感覚の連続で。
その“すごさ”は決して派手なものではなく
むしろ、静かで、深くて、柔らかい。
音に触れた瞬間、
ふわふわの羽布団に包まれるような感覚に陥りました。
ビロードのように光沢があって、
厚みがあるのに、どこか軽やかで柔らかい。
引っかかるものが一切ない。
ざらっとしたものがひとつもない。
耳に、身体に、心に、すーっとなじんでいく。
2曲目のアルベニス「イベリア第2集」でも
それはもう、心地いい〜〜〜♪の一言。
音のハーモニーと、自分の感覚を繋げる言葉をぼんやり探しながら、音を楽しんでいる自分がいました。
わからないからこそ、感じられる
クラシック以外の作品として演奏されたピエール・ブーレーズ作曲「天体暦の1ページ」は、いわゆる現代音楽に分類される曲でした。
現代音楽には、どこか身構えてしまう自分がいます。
だって、何が飛び出してくるのかまったく予測がつかないんですもの。
クラシックのような構造の安心感がなくて、油断してると置いていかれそうになる。
でも、旅先でコンテンポラリーアートに触れるうちに、
少しずつその“わからなさ”を楽しめるようになってきた気がします。
「理解しなきゃ」と思わず、「わからなくてもいいんだよ」って思えたら、
“わからない”という状態が、案外心地よいものに変わってきました。
永野さんが今回演奏された「天体暦の1ページ」も、まさにそんな体験でした。
強弱の対比、音が消えたあとの空間に残る余韻。
微細な音の変化をじっくりと味わえるような、豊かな世界。
言葉にはできないけれど、感じられるものがそこにありました。
“わからない”は、決してネガティブなものじゃない。
それは、まだ知らない世界が始まるサイン。
花の世界も同じです。
最初はわからないことばかり。と感じるかもしれないけれど、
その先には、自分の感覚と静かにつながる時間が待っています。
出会いのきっかけに、感謝
永野英樹さんは、現在もフランスに拠点を置いて、ヨーロッパ各地で活躍されているそう。
私は直接のご縁はないけれど、友人の知人ということで、どこか親近感を抱いちゃいます。
世の中には、まだまだ私の知らない素晴らしい音楽家がたくさんいて。
でも、こちらからその世界に飛び込むには、ちょっとしたきっかけが必要です。
だからこそ、「絶対に聴いてみて」と勧めてくれた友人のひとことが、
私にとって大切な扉になりました。
こんなふうに、人とのご縁が新しい世界を運んできてくれます。
そのありがたさを、またひとつ噛みしめた夜でもありました。
”わからない”は新しい扉
このリサイタルを通じて、”わからない”という感覚ってとても大事だと、改めて思いました。
多くの人は、わからないと思った瞬間に、そこで立ち止まってしまう。
戸惑い、不安になって、心を閉じてしまいます。
でも実は、”わからない”って、
新しい扉が目の前に現れたサインなのかもしれません。
花の世界でも、それは全く同じです。
コルメにいらっしゃる初心者の方たちがよく口にするのは、
「花のことは全然わからなくて…」という言葉。
でも、私はそれを聞くといつも嬉しくなります。
なぜなら、その”わからなさ”の先に、きっとその人だけの感性が待っているから。
わからないことを恐れず、構えず、
ただ、自分の感覚に意識を向けてみる。
そこから、世界は大きく広がっていく。
そんなことを、音楽を通してまたひとつ教えてもらえた夜でした。